
11月に東京を中心に開催される聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」に向け、4月2日デフサッカー男子日本代表が東京・国立競技場で日本フットボールリーグ(JFL)のクリアソン新宿と親善試合を行なった。
デフサッカーの国立開催は初めてで、平日の19時キックオフの試合に約3800人が来場した。
デフ代表は0―2で敗れたが、主将のGK松元卓巳は「日の当たらない代表が、夢の舞台でサッカーができる素晴らしい機会をいただき感謝している」と感激の思いを語った。
デフ代表選手たちは健常の日本代表と同じデザインのユニホームを着用し、JFLのチームと堂々と渡り合った。
デフとは英語でDeafとあらわし、「耳がきこえない」という意味である。
実際のデフアスリートたちは、耳がきこえない、きこえにくいなど聴力には差があると聞く。
デフリンピックや世界選手権では参加者全員がプレーする時の補聴器着装が禁じられているそうだ。
聴覚障がいスポーツには、パラリンピックのように障がいレベルによるクラス分けがない。
補聴器で難聴を補えるレベルの選手もいれば、全く音の聞こえない選手もいるわけで、多様な障がいレベルをピッチの中ではイコールの条件にする考えだと聞く。
スポーツにおけるフェアネスの思想の一つだと、私は解釈している。
一般サッカーとルールは全く同じだ。
ピッチ上の人数、試合時間、ピッチサイズなど差異はない。
デフサッカーの主審は、笛とフラッグ両方を使用し試合を裁くことだけが違いである。
ホイッスルを音で認識できないためだが、それ以外は競技場にいても一般サッカーとの違いを感じることは全くと言っていいほどない。
実際に4月2日、国立競技場にいた私にとっては、侍ブルーと全く同じデザインのユニフォームを着こんだデフ日本代表のイレブンが聴覚障害があり、そのことで思うようにプレーできないように感じることは一切なかった。
発声によるお互いの指示はきこえないから連携が難しいのかと思ってみていたが、彼らは手話を頻繁に使用することもなくアイコンタクトなどで見事に通じ合っていた。
そして応援席の様子と言えば、手話をベースに、デフ選手らが考案した動作で応援する「サインエール」が実施され、多くのサポーターが参加していた。
ピッチへパワーを送るサポーターの応援が視覚的に伝わり、選手にとって大きな励みとなったに違いない。
人には苦手なものがある。
勉強が苦手、人前で話すのが苦手、スポーツが苦手・・ほとんどの人が自分の苦手を自覚して生きている。
多様性の社会と言われて久しいが、人はそれぞれ特徴があり、得意なこともあれば苦手なものもある。
そう、得意なもの、苦手なものがあるから、生きている人は様々だ。
デフという障害を持つ場合、直接のコミュニケーション手段が苦手なのだといえるだろう。
聴覚や視覚に障害があったり、四肢を自由に動かせないで車いすが必要であるなどの人達の生活においては、健常者には想像もつかないほどの不自由さがあるに違いない。
だから、そうした障害や不自由さを苦手と表現するのは失礼にあたるかとも考えたが、国立競技場で観たデフサッカーでは、この苦手という表現が許されるのではないかと思えるほど、クリアソンと対等に堂々と勝負をしていた。
つまり耳が聞こえないこと自体は、ピッチ上においては彼らの苦手な領域ではなく、プレーの一つ一つの中で得意なプレーも、少し不得意なプレーも持ち合わせて戦っていたと思えた。
そしてそれらをすべて自身の個性としながらも、よりよいサッカーするために努力をしているのは全てのサッカーアスリートとして共通なことなのだとも改めて感じた。
この試合では、長身でヘッドの競り合いに強い選手もいれば、ドリブルに長けている選手もいた。
フィジカルでは引けをとらない選手が多かったが、最後の局面でシュートまでもっていく突破力は少し苦手なようにも映った。
普段からより高みを目指して個人もチームとしても、苦手なプレーを克服し、個を磨く努力をしているのだとも思った。
おそらく今回の0対2の敗戦から、またチーム全体で弱点を修正し、デフリンピックでは世界一を目指していくはずだ。
2023年に世界選手権で準優勝しているデフ日本代表の活躍に期待したい。
苦手ということでは別の視点から、キャプテンのGK松元卓巳が以前に語っていたのを記事で見た。
「チームが強くなるには、技術を高めるだけでなく、選手同士のコミュニケーションがとても大切です。ただ、私には大きな問題がありました。デフサッカーの試合中は、補聴器を外し、チームメートとアイコンタクトや手話でコミュニケーションをとらなければならない。でも、私は手話ができませんでした。手話のみで会話をする選手もいたが、何を話しているのかわからず、耳が聞こえないのと同じ状況でした。健常者の中で感じた疎外感を、まさかデフサッカーの仲間の中でも感じるとは。中途半端な自分に対するもどかしさを何とかしようと、そこから手話を学び始めました」と。
聴覚障害のある人が、すべて手話によるコミュニケーションが得意なわけではないということだ。
そういえば知り合いのデフバレー関係者も、生まれつき耳が聞こえないわけではなかったという理由から、どちらかというと手話が苦手だと明かしてくれたことがある。
手話も学んで使えるが、筆談や音声を文字変換する機器もうまく使用してコミュニケーションを図っていると聞いた。
人間生活の営みの中で、苦手を克服するための自身の努力を怠らない強い意志をもつことの大事さを感じると共に、様々なアプローチで人はそれを実現する力を持っているということを教えられた。
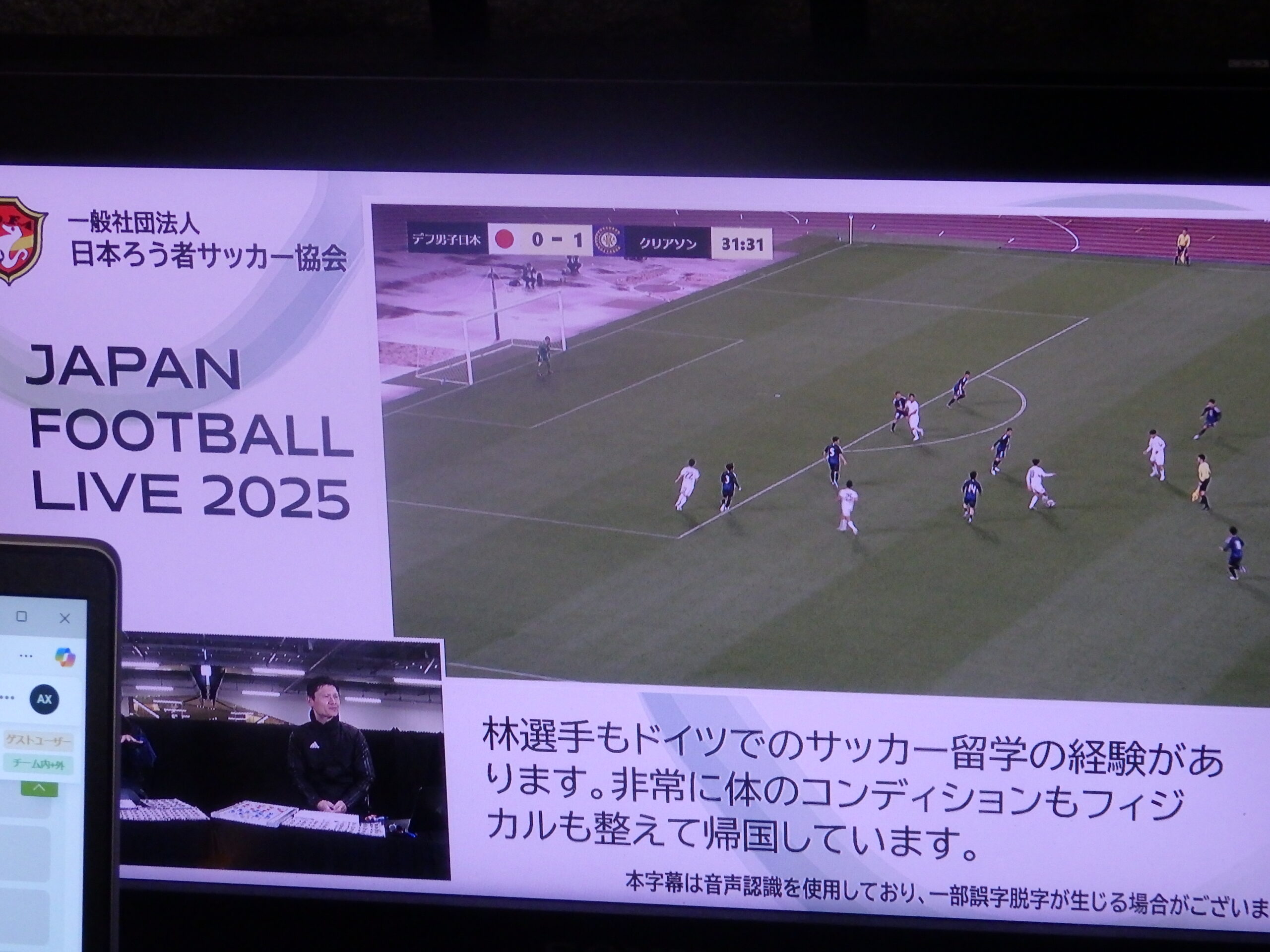
この日のサッカー中継は3台のカメラで制作され、ろう者サッカー協会の公式ユーチューブ配信でリアルタイムで観戦できる仕組みだった。
一般サッカー中継と明らかに違うのは、ワイプ画面で手話を常時ワイプ映像で表示していることだ。
そして手話が得意ではない人向けなのか、併せて実況・解説を手話から読み取り、すぐに文字変換して画面に表示していることだ。
プレーの映像解釈は視覚的に問題ない場合でも、実況や解説の音声を聞き取ることが難しいということを、こうした工夫で見事に解消している放送配信は見事だった。
来たるデフリンピックでは現場に行けない人たちに向けて、大会の模様を公式ユーチューブで配信する予定である。
放送制作経験の豊富な日本の民間プロダクションが、サッカーのみならず全21競技をカバーして一括して制作すると聞いている。
今回のサッカー中継の様に実況、解説の手話展開や、音声を文字に変換して映像表示するなどを全競技にプランした場合、経費も人手もかさむであろう。
それでも多くの聴覚障害の人達にとって、わかりやすい放送配信になることで、大会が大いに盛り上がることを期待している。
そもそも音に関する苦手を克服する手段は様々に講じられている。
きこえない、きこえにくい人が日常生活をスムーズに送るために作られた便利な機器を「情報保障機器」というそうだ。
様々な場面ごとに振動や光で音を表現して知らせる、音を文字に変換して表現するなど、これらはデフリンピックの大会運営、競技の中でも活躍するであろう。
運営全般に文字表示などの工夫がなされるだろうし、陸上競技のスタート合図は、ピストル音でなく視覚で反応できる光表示を利用するなどである。
デフリンピックは今年の11月15日から26日まで、東京都をメイン会場に世界70~80の国と地域から約3000人のアスリートが参加して開催される。
ちなみにサッカー競技は福島県Jヴィレッジで行われる。
日本では初めての開催で、今回は初回から100周年を迎える記念すべき大会となった。
デフリンピック開催の意義は、世界の人々が日本で出会い、デジタル技術なども駆使して「誰もが円滑につながる大会」を実現する過程の中で、共生社会への意識を高めて推進していく一助にするものだと理解している。
パラリンピックでは、車いすでの移動などアクセシビリティ―の拡充を求め、視覚が不自由な方用の音を使用した案内が整備されるきっかけ等が生まれることを目指す。
そして今回のデフリンピックでも、視覚的な機器を配置し、一般にも手話の理解が進むことでコミュニケーションの輪が広がることも期待する。
人との交流に、必ずしも多くの言葉が必要とは限らない。
聴覚障害の方と触れ合うために、少しずつでもいいから手話が理解できたら輪が広がるに違いない。
試合当日、私も「ありがとう」と応援する際の「拍手」の手話を覚えて帰路についた。
健常者の私も、テレビのボリュームは以前より大きくするようになった。加齢とともに急な階段の上り下りは苦手になった。
知り合いのご両親は、高齢で車いすなしには生活が厳しくなった。
誰しもが、得意だったことも苦手になっていくこともある。
しかし、その苦手なことを様々なアプローチで克服していけるのが人間だともいえる。
それも個人の力だけではなく、同じ社会に生きる人々の輪の中で、それは実現していくのだろう。
人間の持つ、お互いに繋がりたいという想いを乗せて、口に出さなくとも手振り身振りで言葉にする「手話」という素晴らしいコミュニケーションツールがある。
技術の進歩による機器を駆使して、高度な筆談も容易になりつつある。
言いたいことがすぐに文字化されることで多くの人との交流もスムーズになる未来はもう近い。
自分だけでは乗り越えられないことでも、人々のいろいろなサポートにより解決していくこともあるだろう。
しかし、これらは一緒になって一つのことを楽しもう、その際にお互いに寄り添おう、そして共に生きようという気持ち無くしては何も実現しないのだと思う。
誰しも苦手なことがある。
それをカバーし合い、助け合うからこそ、お互いの感謝の気持ちが生まれ、よりよい人生を共に過ごす喜びに繋がっていくのではないか。
あの日のデフサッカーのピッチにも、まずサッカーを愛し楽しもう、そのために共にサポートし合い、共に最高のパフォーマンスを目指そうというスピリットに溢れていたことだけは間違いない。